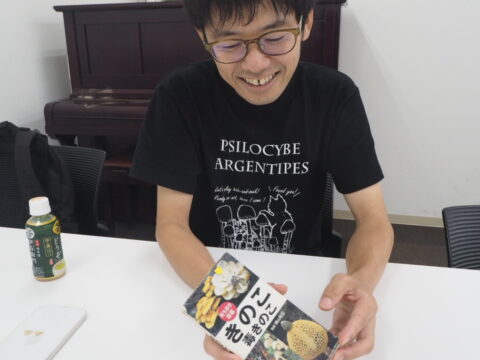神奈川県の丹沢山地は、関東の中でも豊かな山林が残る貴重なエリアです。その恵まれた自然環境を守るために尽力しているのが「丹沢自然保護協会」です。協会は1960年に丹沢札掛を拠点に発足し、2004年にはNPO法人として新たなスタートを切りました。発足から60年以上、丹沢を中心に自然保護活動を続けています。
そして、協会の情報発信を行いながら、表丹沢の案内所のような役割も担っているのが、企業組合「丹沢ホーム」が運営する「ヤビツ峠売店」です。表丹沢の自然を楽しむ人々にとって、憩いの場として親しまれています。
今回お話をうかがったのは、1996年から協会の理事長を務める中村道也さん(77歳)。中村さんは、丹沢札掛の「丹沢ホーム」や、ヤビツ峠にある「ヤビツ峠売店」の運営も行っています。本記事では「丹沢自然保護協会」と「ヤビツ峠売店」がこれまで果たしてきた役割や、今後の展望について紹介します。
目次
人とのふれあいが生まれる「ヤビツ峠売店」

ヤビツ峠売店の店先には、飲料の自動販売機が設置されており、手づくりの焼き菓子も販売されています。店内には「丹沢ホーム」のオリジナルグッズやお土産などが並び、協会が発行する冊子や、表丹沢で開催されるイベントの様子を撮影した写真なども自由に閲覧できます。中央には、年季の入った木製テーブルが置かれ、寒い時期には石油ストーブが設置されます。四季折々の自然を感じながら、一息つける空間です。

取材中、ランナーやロードバイクの愛好家、登山者が次々と訪れていました。中村さんは気さくに声をかけ、登山者の「じゃあ、行ってきます!」という明るい声が店の前に響きます。
ヤビツ峠売店が、営業を開始したのは70年ほど前の昭和30年代。中村さんのお父さんが営林署(国・公有林の管理にあたった役所)の職員から、林業の従事者が休む場所として、運営を頼まれました。また、当時は携帯電話などがなかったため、何かあった時の連絡役としての役割もあったといいます。
「ふかしたサツマイモ1個持って山に登る時代だったから、登山者はほとんど店に入らなくて、最初はただ店を開けているだけだったみたい」と中村さん。
かつては、うどんやラーメンなどの食事も提供していましたが、現在は終了しています。「最近はコンビ二などで飲料や軽食などいろいろ準備してきている人が多いね。時代が変わったよ」
今では売店を訪れる人たちに、時おり珈琲をご馳走しています。そのおいしいコーヒーを通じて、人と人が出会い、つながり、温かい交流の場になっているようです。
「いつの間にか口コミで広まってね。この前も、4人の方がそれぞれ別に入ってきて、最初はみんな離れた席に座っているわけ。私はそれぞれに声をかけながら話していたんだ。そうしたら、お客さん同士も『どこから来たの?』なんて話し始めて、10分もしないうちに、まるで10年来の友達みたいに打ち解けていた。ここは“居場所”のような場所になっているんだなって、改めて思ったよ」と中村さんは目を細めます。
子どもたちが丹沢の自然と本気で向き合う「森の学校」

現在、丹沢自然保護協会は「森の学校」や「植樹活動」といった参加型イベントをはじめ、丹沢の自然保護に貢献する個人研究者や団体に対し、調査費用の一部を助成する「調査・研究活動支援事業」を中心に活動しています。詳細は協会が発行する「丹沢だより」やWEBサイトを通じて発信しています。
中でも「森の学校」は、協会の重点事業として長年続けられてきたプログラムです。「森の学校」が始まったのは、高度経済成長により都市化と環境汚染が進んでいた1972年。自然と触れ合う機会が失われつつある子どもたちの状況に、危機感を抱いた協会が立ち上げました。
対象は小学4年生から中学1年生まで。春・夏・冬の年3回、国民宿舎「丹沢ホーム」に2泊3日で宿泊し、丹沢の自然とじっくり向き合う学びの時間を過ごします。一般的な自然体験教室とは少し異なり、遊び要素は少なく、大学生が学ぶような環境学習を子どもたちにもわかるようにかみ砕いて伝えています。自由に遊ぶ時間は1時間程度ですが、人気が高く、募集開始当日に定員が埋まってしまうこともあるそうです。


プログラムでは、丹沢の自然を知り尽くした講師がレクチャーとフィールドワークを担当します。土・虫・水といった自然の構成要素を、季節ごとのアクティビティを通じて総合的に学びます。三ノ塔まで登ったり、渓流で観察を行ったりと、実際に自然の中に身を置きながら知識を深めていきます。
「例えば山に登って、スギやヒノキの人工林と自然林の違いを説明する。それから翌日、自然林が残る場所へ行き、サンショウウオなどの生き物を探して見つけるんだ。でも人工林の多い場所にサンショウウオはいない。それはなぜか?と子どもたちにも問いかけるようにしているよ。子どもたちに考える力を育ててもらいたいんだ」
屋外の活動だけでなく、室内では食物連鎖の講義や、捕まえた水生生物の名前や特徴、生態を学ぶプログラムなどもあります。また活動の中で経験者の子が初参加の子に声をかけたり、年上の子が年下の子を手助けしたりと、年齢の垣根を越えた助け合いの関係も自然と育まれているそうです。
「一見、豊かに見える丹沢の森も、実は動植物たちのギリギリのバランスで成り立っている」と中村さんはいいます。「次の世代を担う子どもたちには、自然の美しさだけでなく、そのもろさにも気づいてほしい。そして、大人になってからもその学びを忘れず、社会に発信してくれる存在になってほしい」。そんな想いが、この活動には込められています。
50回目を迎えた表丹沢の「植樹活動」

「丹沢から、そして日本列島全体に、生命の息づく森をよみがえらせたい」と、1998年にスタートしたのが植樹活動です。「当時は山が緑になれば何を植えてもいいという風潮もあった。でも日本の山にアメリカ原産の植物が生えていたら、やっぱりおかしいでしょ。だからこそ、昔からその土地に根づいてきた木のDNAを受け継ぐ森をつくりたいと思ったんだ」と中村さんは語ります。
ただ当初は神奈川県産の苗木を大量に確保することが難しい状況でした。そんな中、丹沢自然保護協会の取り組みがメディアに注目され、テレビ番組でも紹介されるように。「その土地に合ったDNAの木々を植えると言っておいて、『やっぱり苗がありません』じゃ格好がつかない」と中村さん。苗木を集めるために、専門業者に神奈川県産の苗を全部買い取ることを前提に注文したり、県の森林試験場に相談したりと、粘り強く行動してきました。
そうした努力が少しずつ実を結び、支援の輪も広がっていきました。2024年10月には活動はついに50回目を迎え、今では春と秋の年2回、丹沢の種子から育てた苗木を1回につき200本以上植えています。

また活動初期は、三ノ塔や大山などの崩壊地で行っていましたが、地元の方の協力により、さらにアクセスしやすい菩提峠近くの斜面へとフィールドを移しました。駐車場から近いため、登山に慣れていない方や子どもでも安心して参加できるのが特徴です。
協会の理念を込めた手ぬぐい

グリーンの手ぬぐいは、植樹活動に参加した方へ感謝の気持ちを込めて配られるものです。森のはじまりから完成までをつなぐ、4種の樹木の葉がデザインされています。森で最初に生える「先駆樹種(※1)」と呼ばれるハン、ウツギ。そして最終的に安定した森「極相林(※2)」の象徴であるブナ、ミズナラです。
「森というと一般的には立派なブナの森が注目されがちだけど、森はブナから始まるんじゃない。まずは先駆樹種が生えて、ヤブ山のような状態から時間をかけて変化していくんだよ」と中村さんは説明します。先駆樹種が生え、約20年という寿命の間に、ヤマザクラやカエデといった次の世代がまわりで育ちます。そして先駆樹種が枯れる頃、次世代の木が本格的に森を担い始める――。表丹沢の森では、そんな自然のリレーが繰り返されているのです。
さらに、植樹活動の50回目という節目を迎え、特別なデザインを施した水色の手ぬぐいも手がけました。そこには、協会の理念を象徴する「空に鳥 森にけもの 川に魚を」という一文も込められています。これは中村さんのお父さんが考えた言葉です。
中村さんは「木を植えて森を育てれば、やがて川ができる。森の中に獣がいて、クマタカも飛び、川に魚が戻ってくる。これが、私たちが目指す自然の姿なんだ」と説明します。クマタカは、森林生態系において食物連鎖の頂点に立つ鳥です。「そのクマタカが丹沢に生息しているということは、この地域の自然が今なお健全で、豊かに保たれている証拠」とのこと。
森を作るには、気の遠くなるような年月がかかります。それでも丹沢自然保護協会のメンバーは、地道な活動を止めることなく、真摯に自然と向き合い続けています。
※1 森林ができ始めるときに最初に生えてくる木の種類
※2 時間が経つと自然にできあがる、安定した森の姿
都市に近い表丹沢で目指す多様な自然のかたち

都心から電車で70分ほどに位置する秦野市。中村さんは「豊かな自然がそのまま残り、観光地化していないのが魅力」と話します。
そして表丹沢は、塔ノ岳のような本格的な登山ルートが多くの登山者に親しまれていますが、丹沢自然保護協会が今後の活動の一つとして考えているのは、その手前に広がる「里山」的なエリアです。里山とは、農林業をはじめとした人々の暮らしと、森林や草原などの自然が共存する地域のことを指します。

「高い山に登るのは難しいという人も、里山だったら『ちょっと行ってみようか』と思える。そういう方たちって、今まで秦野に来ていなかった方だと思うから、新しい利用者が増える可能性もあるよね」
また、中村さんや協会のメンバーは「芝生に入ってはダメ」といった制限の少ない、子どもたちがもっと自由に自然に触れられる場の必要性も感じています。「整備された公園も立派だけど、もっと自然そのものを感じられるような場があってもいい。たとえば、田原ふるさと公園の近くに、みんなの手でそういう場を作れたらいいよね」
中村さんは、里山の保全と再生は環境だけでなく、農業、福祉、教育など多岐にわたる分野に関わると話します。こうした自然空間は、遊び場としてだけでなく、田畑での農業体験や教育、地域交流の場など大きな可能性を秘めているのです。
「今の若い親世代は、草花で遊んだりといった自然体験をあまりしていないかもしれない。そんなとき、地元のおじいちゃんやおばあちゃんが子どもたちに教えてくれたりしたらいいよね。子どもとお年寄りがつながる、そういう場所もあったらいいんじゃないかな」と、都会の子どもたちと地元の高齢者をつなぐ仕組みづくりにも関心を寄せています。
忘れてはならないのが、整備された里山は、近年特に話題となっている鳥獣被害の防止にも効果があるそうです。「昔の里山は、農家の人たちがちゃんと手入れしていた。そうすることで、野生動物にとって居心地の良すぎない環境が保たれていた。人里と動物との間の緩衝地帯みたいなものだね」
表丹沢には、山に登るだけではない、さまざまな自然との関わり方があります。都市近郊にありながら、ありのままの自然をしっかり感じられるのが大きな魅力です。これからも中村さんたち丹沢自然保護協会のメンバーは、その自然の価値を伝えながら、地域を守り、新しい可能性を広げていくでしょう。
国民宿舎 丹沢ホーム
住所:〒257-0061神奈川県秦野局区内丹沢札掛
電話番号:0463-75-3272
公式サイト:https://www.tanzawa-home.com/
アクセス:
・公共交通機関
小田急小田原線 秦野駅より『バス』【秦21】「ヤビツ峠行き」で約45分、終点「ヤビツ峠」下車、徒歩約60分(宿泊者のみ送迎バスあり、要予約)
・車
新東名高速道路 秦野丹沢スマートICより約1時間/東名高速道路 秦野中井ICより約45分
ヤビツ峠売店
住所:〒257-0023神奈川県秦野市寺山
電話番号:0463-75-3272
営業時間:土日祝日 8時~17時
休業日:平日
アクセス:
・公共交通機関
小田急小田原線 秦野駅北口よりバス【秦21】ヤビツ峠行きで約50分、終点「ヤビツ峠」下車、徒歩約1分
・車
新東名高速道路 秦野丹沢スマートICより約45分/東名高速道路 秦野中井ICより約45分
丹沢自然保護協会
公式サイト:https://www.tanzawa-shizenhogo-kyoukai.org