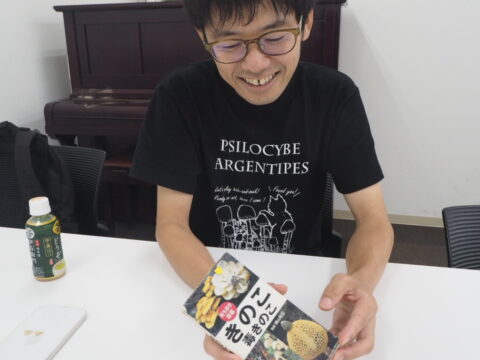神奈川県表丹沢の麓にある秦野市柳川。長年料理人として活躍している白井寛人さんは、 4 年前、この地との運命的な出会いを機に移住し、農地開拓という新たな一歩を踏み出しました。今では開拓した農地で人と食、地域をつなぐ農業体験に取り組んでいます。その活動は大きな注目を集め、募集のたびに定員が埋まるほどの人気を誇っています。
今回は、白井さんに農地開拓のきっかけや、この土地の魅力、開業を目指す農場レストランについてお話を伺いました。自然と向き合い農地を育む、白井さんの里山での暮らしをのぞいてみました。
目次
型にとらわれない発想が、料理人生の原点

幼少の頃にはすでに「料理人になる」と決めていましたね。お客さんの目の前で料理を仕上げるステーキハウスに行ったとき、鉄板の上で次々と生まれる料理の迫力と香りに心を奪われ「自分もこんな料理をつくりたい」と思ったのが、料理を始めたきっかけです。自分が作った料理で周りが喜んでくれるのが、とてもうれしかったのを覚えています。
10 代で「30 歳までに店を持てなければやめる」と心に決め、専門学校やフランスのレストランで料理を学びました。料理技術の土台を築いた後は、アメリカのレストランを視察し、日本に戻って和食の修行も積みました。さらにカナダでも腕を磨きながら、海外と日本を行き来する日々でした。
24 歳のとき、茨城のフレンチレストラン跡を活用して思いがけず自分の店を持つことができました。デフレで外食産業が厳しい時代でしたが、ケータリング(出張料理)や 1 日 1組限定でおまかせコースの提供、実演型の料理講習など新しいスタイルを提案しました。その後、出身地の横須賀に拠点を構え、そこでもケータリングや地域との交流も広げていきます。この間に培った「従来の型にとらわれず、お客様のニーズにマッチした新しい店の形をつくる」という姿勢こそが、自分の原点になっています。
料理人としての新たな挑戦、農地開拓

食材探しやケータリングで日本各地を訪れるうちに、埼玉県飯能市や千葉県我孫子市の農 家の方々と直接つながるようになりました。そこで援農(農業ボランティア)として畑に入り、食材の背景には土や水、気候、そして人の手間ひまがあることを強く実感しました。実際に体験することで、作物がどんな思いで育てられているのかを肌で学んだのです。
しかし料理の世界では、どれほど丁寧に育てられた野菜も、料理人の手に渡った瞬間に「料理」となり、評価の中心は「誰が作ったか」に偏りがちです。その一方で、私たち料理人が惹かれる個性的な野菜を育てる農家の方々は、大量生産に頼らず手間をかけて野菜を育てていますが、その努力が十分な収入に結びついていないという厳しい現実を抱えています。
こうした状況を知るほどに、自分は農家の方々に支えられるばかりだと感じました。料理人として恥ずかしく思えたのです。自分だけが光を浴びるのではなく、どうすれば農家を支えられるのか、と考えるようになりました。
ただ野菜の価格を上げるだけでは、問題は解決しません。農家の方々も「お金よりも良い食材を届けたい」という思いで取り組んでいるからです。
また、日本では形の曲がった野菜は規格外とされますが、ヨーロッパでは「味や個性」が重視されます。私自身、フランスで修行していた頃は、ニンジン一つとっても、煮込み用やペースト用など種類が豊富で、料理の幅がぐんと広がりました。だからこそ、日本でも農薬などに頼らず、その土地に合わせた農法に挑む農家を支えることが大切だと感じています。
さらに、作物は農家の方々の努力だけでできるものではありません。土の微生物、森の保水力、川の流れ、虫の営み……自然の循環すべてが関わっています。しかし、人の暮らしの変化一つで、その環境は簡単に崩れてしまう。つまり農家を支えるとは、食材を守るだけでなく、自然環境そのものを守ることでもあるのです。 料理人としての私の役割は、ただ料理を作ることではなく、農家の方々を取り巻く環境そのものや、生き物と自然とのつながりを守ること。そう気づいたとき、農地を開拓することが、取り組むべき第一歩だと感じました。
偶然の出会いから始まった秦野への移住

農地を開拓し、有機・無農薬の栽培を実践するためには、耕作放棄地を活かすことが理想だと考えました。耕作放棄地には化学肥料に頼らない、自然のままの菌や微生物が豊かに残っているからです。整備さえすれば、作物を力強く育てられる環境になります。
そのため土地選びは重要でした。求めていたのは、人の手をほとんど必要としない原野のようなところではなく、人が暮らしながら都市と自然を共存させ、守っていくことができる場所。そして地域に自然や生き物を大切にし、水や環境を守る文化があるかどうか、そういった視点も持ちながら、地元の横須賀や千葉、長野、そして東北や九州などあらゆるところを巡りました。さらに行政の姿勢も考慮しながら、自分の目指す形に合う土地を探し続けたのです。
そうして辿り着いたのが秦野市柳川です。
ここに来たのは本当に偶然でした。特に目的地もなく車であちこち走り回り、信号待ちで進む方向を直感的に変えて……そしてふと目の前に広がったこの柳川の風景を見た瞬間、「もう、ここしかない……!」と強く感じましたね。
その後、地域の方々と出会い、農地を借りるためのサポートや行政との橋渡しをしていただき、さらに竹林整備などの活動にも参加する中で、ご縁が広がっていき、農地を借りられるようになりました。まさに運命的な出会いでした。米作りを始める前に地元の神社と協力して奉納するなど、地域とのつながりも大切にしています。ポスティングなどで呼びかけ、100 人近くの方が集まってくれました。
米作りについては、九州の農家と提携して学んだ経験はありましたが、ゼロから挑戦するのは初めて。最初はわずかな区画を予定していたところ、地主の方から「どうせなら全部の区画をやってみたら?」と提案され、1 年目から 2 反 8 畝(約 2,800 平方メートル)という大きな区画に挑みました。

水の管理は難しいといわれますが、日々田んぼを観察する中で稲の状態を掴めるようになり、自然と水量の調整もできるようになりました。おかげで初年度から収穫でき、料理人としてこだわっていた「はさがけ」(竹に稲をかけて天日干しする方法)にも挑戦できました。この地域で整備した竹林の竹を利用して行うことで、地域の循環にもつながったのです。

田んぼは企業研修や田植え体験イベントなどにも活かし、一般の方々にも米作りに参加してもらっています。生産量は多くありませんし、田んぼを広げればよいというものでもありません。手間をかける分だけ効率は下がります。だからこそ、口コミを中心に本当に必要としてくださる方に届けています。今後レストランが始まれば、一般販売はさらに限られるかもしれませんね。
食と自然をつなぐ農場レストランの実現に向けて

現在、開拓した地では、田植え・稲刈りや竹林整備など、農業や自然を楽しむ体験イベントを行っています。イベントの際には、参加者と一緒に自然の中で食事を楽しむなど、将来的には「農場レストラン」の開業を目指しています。レストランを営業するには、農地転用や各種許可申請、水道・下水などのインフラ整備が必要です。現在は、そうした課題を一つひとつ検討しながら、無理のない形を探っているところです。
私が目指しているのは、単に料理を食べるための場所ではありません。田んぼを渡る風、畑で揺れる野菜、森の匂い、鳥の声、この土地に積み重なってきた「記憶」や「営み」を一皿に込め、食べることを通じて自然や人の暮らしを思い出すきっかけになるような体験を届けたいのです。

構想しているのは、レストランという形にとどまらず、資源を守りながら、農業や林業、地域の人や企業が交流するプラットフォームのような拠点です。そのために必要なのは食に関する「楽しさ」や「喜び」です。収穫した野菜でバーベキューしたり、目の前で調理した料理を味わったり。そのようなシンプルな体験こそ、食材の一番おいしい瞬間を伝えられると考えています。
移住して4年。課題は山積みですが、農場レストランの実現はゴールではなく、この地域全体をどう未来につないでいくかが最大のテーマです。農業や食を軸に、人がつながり、楽しみながら持続可能な暮らしを築いていく。その拠点として、この土地とともに成長していけたらうれしいですね。
表丹沢、柳川で見つけた暮らしの魅力

ここで暮らすこと自体が、私にとって大きな意味があります。窓を開ければ表丹沢の山並みが広がり、畑の息づかいを肌で感じる日常。その一つひとつが喜びであり、料理人としての活動や地域の保全、農業体験の運営に自然につながっていきました。
以前住んでいた地域は利便性がある反面、自分の手で環境を守る実感は得にくいところで した。しかしこの里山には、森や水、田畑、虫や草、微生物が息づく「生き物の里」としての自然が残っており、その循環を暮らしの一部として受け入れ、静かに守り続けてきた地域の人々のまなざしを感じます。こうした環境に向き合いながら、地元の方々や移住者とともに守ることができます。草刈りの音や湧水の冷たさ、木陰を抜ける風に触れるたび、ここにはまだ見えない価値が生きていると実感します。

もともとは、農家の方々の手助けになればと考えて始めましたが、今では能動的に関わることで得られる学びや喜びの方が大きいと感じています。田んぼや畑で汗を流すことは、ただの農作業ではなく「日々の楽しみ」となりました。その価値を多くの人にも体験してもらいたい。そうして農業体験で生き生きと過ごす参加者の姿を見るたび、私自身もうれしくなります。
特にこの秦野市の上地区(菖蒲、三廻部、柳川、八沢を含む地区)は、実際に暮らしてみると、自然だけでなく、文化や里山の営みが今も色濃く残っています。ここで育つ農作物はただの食材ではなく、この土地の風土を映し出しているのです。
私が感じるのは、この場所には大きな発展の可能性があるということ。といっても、工場や企業誘致によるものではなく、人と地域の大切さがにじみ出るような発展です。料理人としても、ここ以上の土地はありません。近い将来、農場レストランを開業し、食事や体験を通じてこの里山の価値を多くの人に伝えていきたいですね。
料理することは暮らしをつくること。料理や食卓が生まれる風景を支えることは、未来へ命をつなぐこと。森を手入れし、作物を育て、水や土、生き物と向き合いながら、柳川のこの土地の循環を次の世代につないでいく。私にとってこれこそが「OMOTAN ライフ」です。
■白井寛人さん HP(株式会社ファウナバランス)
https://faunabalance.com/